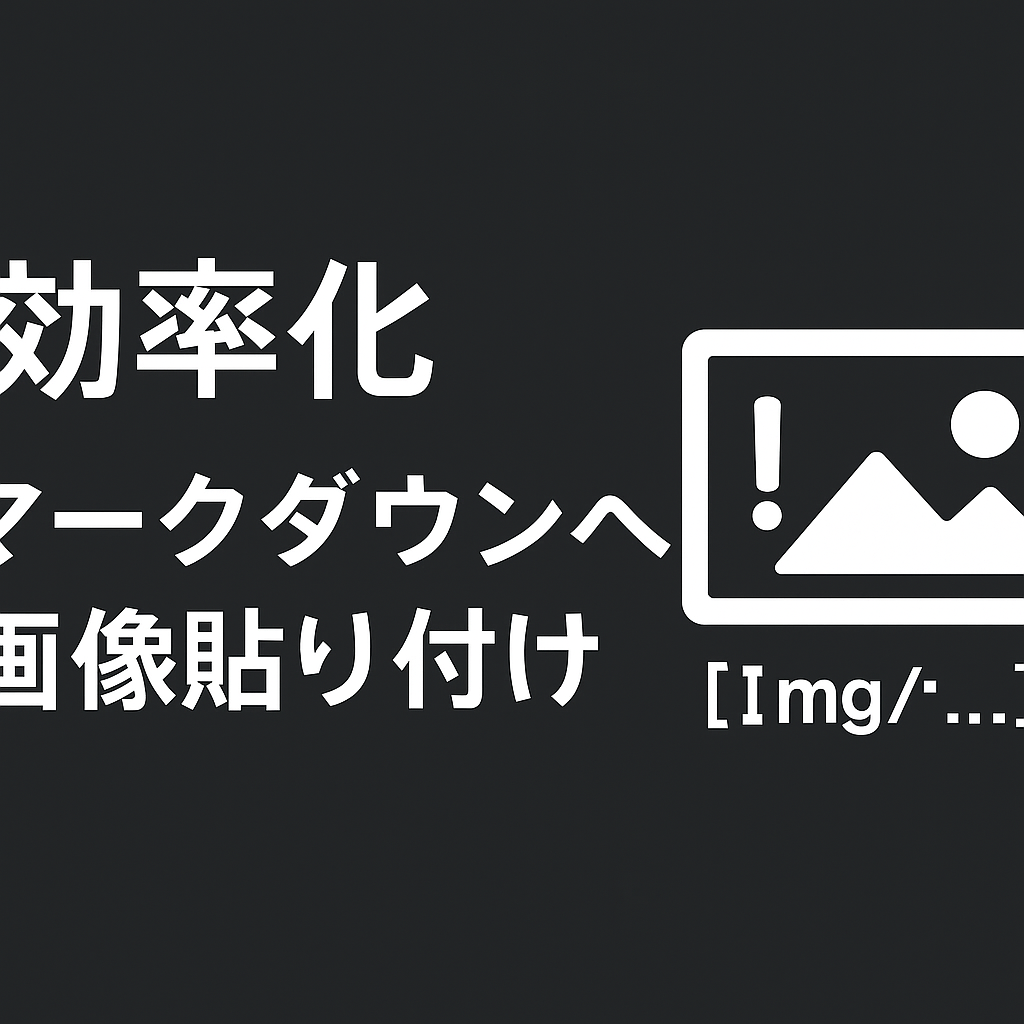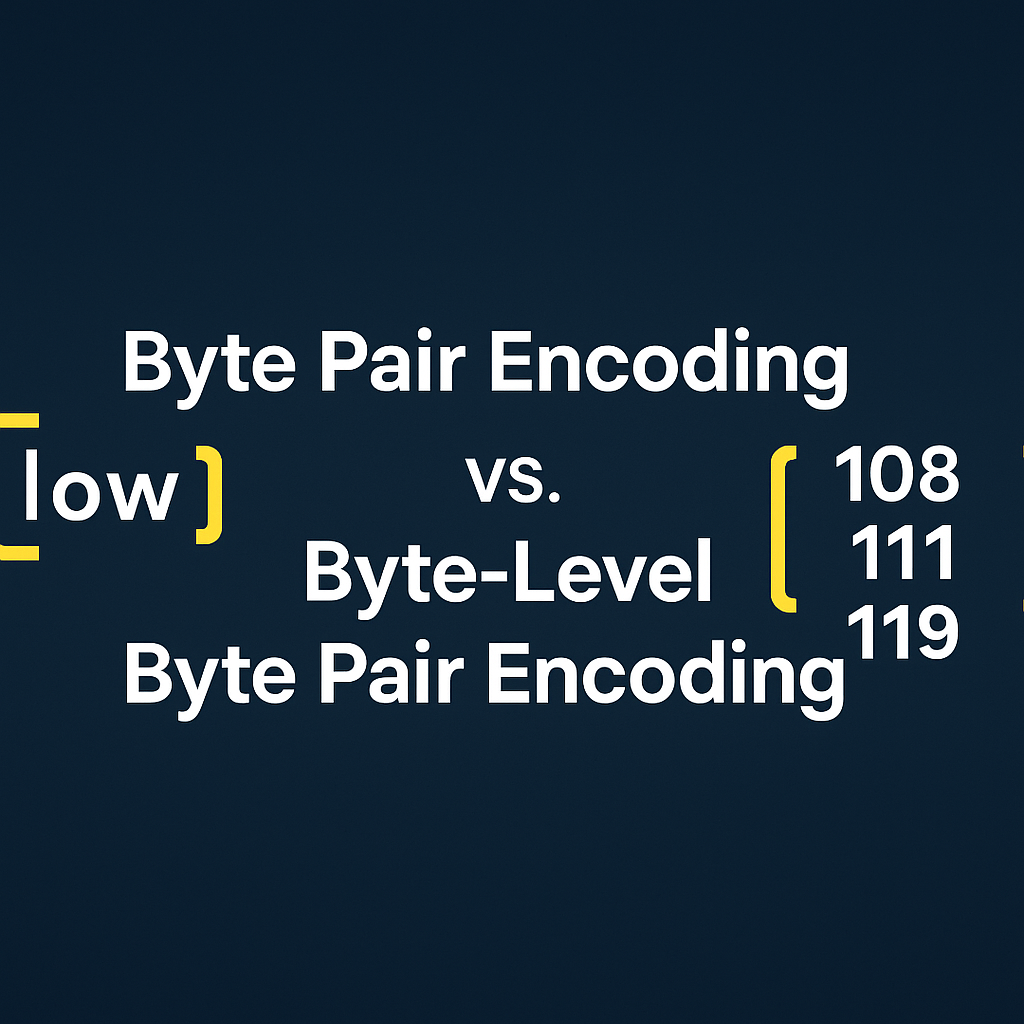B-Treeインデックスの仕組み
データベースのパフォーマンス向上において、インデックスは欠かせない技術です。中でもB-Treeインデックスは最も広く使われており、その効率性の秘密を理解することで、より良いデータベース設計が可能になります。


データベースのパフォーマンス向上において、インデックスは欠かせない技術です。中でもB-Treeインデックスは最も広く使われており、その効率性の秘密を理解することで、より良いデータベース設計が可能になります。
B-Treeインデックスとは
B-Treeは「Balanced Tree(平衡木)」の略で、データを階層的な木構造で管理するインデックス技術です。本の索引のように、大量のデータから目的の情報を素早く見つけるための「地図」として機能します。
例として、社員テーブルの年齢データ [22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35] にB-Treeインデックスを作成すると、以下のような構造になります:
[28] ← ルートノード
/ \
[25] [30] ← 中間ノード
/ \ / \
[22] [26] [29] [31,35] ← リーフノード
驚異的な検索効率
B-Treeの真価は検索効率にあります。1000万件のデータがある場合:
- 線形検索: 平均500万回の比較
- B-Tree検索: 平均23回の比較
この劇的な差は、B-Treeが O(log n) の計算量で動作するためです。
等価検索の例
「年齢30歳」を検索する場合:
- ルートノード[28]をチェック → 30 > 28なので右へ
- 中間ノード[30]で発見 → 該当データを直接取得
わずか2ステップで目的のデータに到達できます。
範囲検索の威力
B-Treeのリーフノードは連結リストのように繋がっているため、範囲検索も高効率です。「年齢25-30歳」を検索する場合:
- 開始点(25歳)をB-Tree検索で発見
- リーフレベルで順次移動:[25] → [26] → [28] → [29] → [30]
- 該当するすべてのデータを連続取得
B-Tree構築の秘密:ルートノードはこうして決まる
多くの人が「ルートノードは平均値?」と考えがちですが、実際は分割過程での中央値昇格によって決まります。
データを順次挿入する過程を見てみましょう(各ノードの最大容量を3個と仮定):
ステップ1: [22, 25, 26] → まだ1ノードで収まる
ステップ2: 28を挿入 → [22, 25, 26, 28] → 容量オーバー!
分割発生:
[26] ← 中央値が昇格してルートに
/ \
[22,25] [28] ← 左右に分割
この過程を繰り返すことで、最終的なB-Tree構造が決定されます。重要なのは、ルートノードの値はデータの平均値ではなく、分割時の中央値だということです。
バランスが生む安定性
B-Treeの「Balanced(平衡)」という名前は、すべてのリーフノードが同じ深さにあることを意味します。これにより:
- どのデータを検索しても、ほぼ同じステップ数で到達
- 挿入・削除操作でも構造が崩れない
- 安定したパフォーマンスを維持
実践での活用
-- よく検索される列にB-Treeインデックスを作成
CREATE INDEX idx_employee_age ON employees(age);
-- 範囲検索が高速化
SELECT * FROM employees WHERE age BETWEEN 25 AND 30;
-- ソート処理も最適化
SELECT * FROM employees ORDER BY age;
まとめ
B-Treeインデックスは、木構造の階層性と連結リストの連続性を併せ持つ優れた技術です。その効率性は数学的な計算量の削減だけでなく、実際のディスクI/O最適化にも寄与しています。
データベースの心臓部とも言えるB-Treeの仕組みを理解することで、より効果的なインデックス戦略を立てることができるでしょう。大量データを扱うシステムにおいて、B-Treeは今後も重要な役割を果たし続けるはずです。

通りすがりのラマ🦙
このブログでは個人開発で得た知見や興味のあるテクノロジーに関する記事を執筆します。 日々公開されている情報に助けられているので、自分が得た知見も世の中に還元していければと思います。 解決できないバグに出会うと、草を食べます。🦙🌿 経歴: 情報工学部→日系SIer→外資系IT企業 興味: Webアプリケーション開発、Webデザイン、AI 趣味: 個人開発、テニス